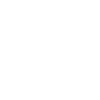このサイトは 「PASSIVE STYLE」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
脱炭素志向型住宅とは、エネルギー消費を最小限に抑え、二酸化炭素(CO₂)の排出を可能な限り削減した住宅のことを指します。政府が掲げる「2050年カーボンニュートラル」の実現に向け、住宅分野においても省エネルギー性能の向上が求められています。建築時のエネルギー消費を削減することはもちろん、住宅の使用期間中も効率的にエネルギーを活用できるよう設計されていることが特徴です。
従来の住宅は、電力やガスを多く使用し、その結果として大量のCO₂を排出していました。しかし、脱炭素志向型住宅では、建材や設備の工夫によってエネルギー消費を抑え、再生可能エネルギーを積極的に取り入れることで、環境負荷を大幅に低減します。このような住宅の普及は、個人の暮らしだけでなく、社会全体の脱炭素化にも大きく貢献します。
GX志向型住宅とは?
GX(グリーントランスフォーメーション)とは、環境負荷を低減しながら経済成長を促進するための取り組みを指します。住宅分野においてもGXが重要視されており、脱炭素化を実現するためにさまざまな技術が導入されています。
脱炭素志向型住宅では、まず断熱性能が大幅に向上しています。高断熱・高気密の構造によって、外気の影響を受けにくくし、冷暖房効率を高めることでエネルギー消費を削減します。加えて、住宅の屋根や外壁には太陽光パネルが設置され、自家発電を行うことが一般的になっています。発電した電力は、家庭内で消費するだけでなく、余剰分を蓄電池に貯めて夜間や天候の悪い日に使用することもできます。さらに、蓄電池を備えた電気自動車と連携させるV2H(Vehicle to Home)の技術を活用すれば、より効率的なエネルギーマネジメントが可能になります。
また、HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)を導入することで、家庭内のエネルギー使用状況を可視化し、無駄を省くことができます。たとえば、照明やエアコンの自動制御機能を活用すれば、使っていない部屋の電気を消すといった省エネ対策が容易になります。住宅全体のエネルギー消費を最適化することで、電力使用量を削減し、持続可能な住まいを実現できます。

脱炭素志向型住宅のメリット
光熱費の削減
脱炭素志向型住宅の大きなメリットのひとつは、光熱費を大幅に削減できることです。高断熱・高気密の設計により、室内の温度を一定に保ちやすくなり、冷暖房の使用頻度が減少します。たとえば、一般的な住宅では冬場に暖房をつけても外気によって室温が下がりやすく、頻繁に暖房を使用する必要があります。しかし、脱炭素住宅では断熱性能が高いため、一度温まった室内は長時間暖かさを保つことができ、冷暖房にかかる電力消費が大幅に削減されます。
また、太陽光発電システムを導入することで、自家発電による電力供給が可能になります。日中に発電した電力を蓄電池に貯めることで、夜間にも使用できるため、電力会社からの購入電力量を大幅に減らすことができます。さらに、発電した電力を売電することで、光熱費の負担をさらに軽減できる場合もあります。
快適な住環境
脱炭素志向型住宅は、省エネルギー性能の向上だけでなく、住み心地の面でも優れています。高断熱・高気密の設計により、外気温の影響を受けにくく、年間を通じて快適な室内環境を維持できます。特に冬場は、床や壁が冷たくなりにくいため、室温のムラが少なく、快適な暖かさを保てます。また、夏場は外部からの熱の侵入を抑えることで、冷房の効率を高め、涼しい室内環境を実現します。
さらに、適切な換気システムを導入することで、室内の空気を清潔に保つことができます。従来の住宅では、窓を開けないと換気が十分に行えない場合がありましたが、脱炭素住宅では、24時間換気システムを利用することで、新鮮な空気を取り入れながら、二酸化炭素やハウスダストなどの有害物質を排出することができます。これにより、シックハウス症候群のリスクを軽減し、健康的な住環境を維持することが可能になります。
資産価値の向上
脱炭素志向型住宅は、将来的にも資産価値が維持されやすい特徴があります。現在、多くの国で省エネ性能の高い住宅が推奨されており、今後の住宅市場においても、省エネ住宅の需要は高まると予想されます。そのため、脱炭素住宅を建てることは、長期的な資産価値の維持にもつながります。
また、環境性能の高い住宅は、売却時にも有利に働くことがあります。たとえば、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)認定を受けた住宅は、省エネ性能が高く、光熱費の削減が期待できるため、購入希望者にとって魅力的な選択肢となります。このように、脱炭素住宅は、経済的なメリットだけでなく、将来的な資産価値の向上という観点からも優れた選択肢と言えるでしょう。
脱炭素志向型住宅のデメリット
初期コストの高さ
脱炭素志向型住宅を建てる際に最も大きな課題となるのが、一般的な住宅に比べて初期費用が高くなることです。高性能な断熱材を使用し、気密性を向上させるためには、通常よりも高価な建材や施工技術が必要になります。また、太陽光発電システムや蓄電池の導入には数百万円単位の費用がかかる場合もあり、建築費用全体が大幅に増加する可能性があります。
特に、最新のエネルギーマネジメント技術を取り入れようとすると、さらなるコスト増につながります。HEMS(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)を導入することでエネルギーの最適管理が可能になりますが、そのためには専用の機器やシステムの設置が必要となり、これも初期投資の一部として考慮しなければなりません。
一方で、これらの初期費用は長期的に見れば光熱費の削減によって回収できる可能性があります。しかし、回収までにかかる期間は住宅の仕様やエネルギー使用状況によって異なり、短期間で元が取れるとは限りません。そのため、コスト回収のシミュレーションを事前に行い、どの程度のメリットがあるのかを十分に検討することが重要です。
メンテナンスの必要性
脱炭素志向型住宅は、先進的な技術や設備を多く採用しているため、定期的なメンテナンスが欠かせません。たとえば、太陽光発電システムは長期間にわたって利用できますが、パネルの汚れや劣化によって発電効率が低下する可能性があります。そのため、定期的な点検や清掃が必要になります。また、蓄電池についても寿命があり、一般的には10~15年程度で交換が必要になる場合があります。
換気システムも重要なメンテナンス対象のひとつです。高気密住宅では、計画的な換気が不可欠であり、24時間換気システムが設置されていますが、フィルターの清掃や交換を怠ると、空気の質が悪化し、快適な室内環境が維持できなくなります。特に、フィルターの詰まりは換気効率を低下させるため、定期的な点検と清掃が必要になります。
また、スマートホーム技術を取り入れている場合、システムのアップデートや不具合対応といったメンテナンスも発生することがあります。HEMSの管理システムが古くなると、機能が制限されることがあり、最新のシステムと互換性がなくなるケースもあるため、アップデートや買い替えのコストが発生する可能性があります。
施工業者の選定が難しい
脱炭素志向型住宅の建築には、高度な設計・施工技術が求められます。そのため、すべての住宅メーカーや工務店が対応できるわけではありません。特に、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)やパッシブハウスといった高性能住宅を建てる場合、専門的な知識を持つ業者を選ぶ必要があります。
施工業者によっては、断熱や気密施工の品質に差があるため、適切な業者を選ばないと、十分な性能が発揮されない可能性があります。たとえば、気密施工が不十分だと、せっかく高性能な断熱材を使っていても、すき間風によって断熱効果が損なわれることがあります。また、太陽光発電や蓄電池の設置に関しても、経験の少ない業者が施工すると、配線の不具合や発電効率の低下といったトラブルが発生するリスクがあります。
さらに、施工業者の選定だけでなく、設計段階での検討も重要です。脱炭素住宅の効果を最大限に発揮するためには、日射の取り入れ方や通風の設計、建物の方位なども考慮しなければなりません。これらの要素を適切に設計できる建築士や設計士と連携することが求められます。そのため、業者選びには時間をかけ、実績や評判をしっかりと確認することが大切です。
補助金に依存するリスク
脱炭素志向型住宅を建てる際、多くの人が補助金を活用しようと考えます。しかし、補助金制度は毎年内容が変わる可能性があり、申請時期や条件によっては受給できないこともあります。特に、国や自治体が提供する補助金には予算の上限が設けられており、申請が殺到すると早期に締め切られることもあります。そのため、補助金を前提とした資金計画を立ててしまうと、万が一受給できなかった場合に予算オーバーとなり、計画の見直しを迫られる可能性があります。
また、補助金の要件を満たすために、本来必要のない設備を導入するケースもあります。たとえば、補助金の条件として特定の断熱性能や設備の導入が求められる場合、実際には不要な機能を追加せざるを得ないこともあります。その結果、補助金を受け取ったとしても、トータルのコストが上がってしまい、最適な住宅設計ができなくなることも考えられます。
そのため、補助金はあくまで「プラスアルファの支援」として考え、補助金がなくても無理なく建築できる計画を立てることが重要です。
脱炭素志向型住宅に利用できる補助金制度

国の補助金制度
脱炭素志向型住宅の普及を促進するため、日本政府はさまざまな補助金制度を設けています。その中でも代表的なのが、経済産業省と国土交通省が連携して実施する「脱炭素志向型住宅の導入支援事業」です。この事業では、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)基準を大きく上回る省エネルギー性能を備えた住宅の建築に対して補助金が支給されます。
この補助制度の対象となるのは、新築の戸建住宅および新築の集合住宅で、1戸あたり160万円の補助が受けられます。ただし、補助金を受けるためには、住宅が以下の条件を満たしている必要があります。
一次エネルギー消費量の基準(BEI)が0.65以下であること(省エネ性能のみの場合)
BEI(Building Energy Index)は、建物のエネルギー効率を示す指標です。数値が小さいほど省エネ性能が高いことを意味し、0.65以下に抑えることで補助対象となります。
一次エネルギー消費量の削減率が100%以上であること(再生可能エネルギーを含む場合)
太陽光発電や蓄電池などを活用し、建物が消費するエネルギーと同等以上の再生可能エネルギーを生み出すことで、エネルギー収支をゼロにすることが求められます。
断熱等性能等級6以上であること
住宅の断熱性能を示す「断熱等性能等級」は、国が定める基準で、等級6以上を満たす住宅のみが補助対象となります。これは、住宅の外壁や窓の断熱性能が極めて高い水準であることを意味します。
なお、補助対象外となる住宅もあるため注意が必要です。たとえば、土砂災害特別警戒区域や市街化調整区域のうち、特定の災害リスクが高いエリアに建築される住宅は、原則として補助の対象外となります。
自治体の補助金制度
国の補助金制度に加えて、各自治体も独自の補助金を設けています。自治体ごとに制度の内容が異なるため、居住予定の地域でどのような支援が受けられるのかを確認することが重要です。
多くの自治体では、太陽光発電システムや蓄電池の導入に対する補助が用意されています。たとえば、東京都では「ゼロエミッション住宅」推進の一環として、ZEH水準の住宅に対する助成金を提供しており、さらに高い省エネ性能を持つ住宅には追加の補助が行われる場合があります。また、北海道や東北地方など寒冷地では、高性能な断熱材の導入を支援する補助金が設定されているケースもあります。
自治体の補助金制度は毎年内容が変更されることが多いため、申請を検討する際には最新の情報を自治体の公式ウェブサイトで確認することをおすすめします。
税制優遇措置
脱炭素志向型住宅を建てる際には、補助金だけでなく税制優遇措置も活用できます。これには、住宅ローン減税、固定資産税の軽減措置、不動産取得税の減額などが含まれます。
住宅ローン減税は、一定の省エネ基準を満たした住宅に対して、住宅ローンの残高に応じた減税が受けられる制度です。特にZEH基準を満たした住宅は、減税の対象として優遇される傾向にあります。
また、長期優良住宅や低炭素住宅に認定されると、登録免許税や不動産取得税の軽減措置が適用される場合があります。たとえば、登録免許税が通常の税率よりも引き下げられ、取得時のコストを抑えることが可能になります。
補助金活用時の注意点
申請手続きと期限
補助金の申請には、事前の準備が欠かせません。特に、補助金には受付期間が設定されており、予算の上限に達すると受付が終了するケースもあります。そのため、住宅の設計段階から補助金を活用する計画を立て、早めに申請の準備を進めることが重要です。
補助金申請には、住宅の省エネ性能を証明する書類が必要になります。これには、設計図面、建築確認申請書、エネルギー計算結果などが含まれます。書類の準備に時間がかかるため、工務店や設計事務所と連携しながら進めることが求められます。
補助金頼みの計画リスク
補助金制度を活用することで、住宅の建築費用を抑えることができますが、補助金を前提とした資金計画を立てるのはリスクを伴います。補助金制度は年度ごとに変更される可能性があり、申請時期によっては受給できないこともあるため、補助金なしでも無理なく建てられる資金計画を立てることが大切です。
また、補助金の要件を満たすために、本来必要のない設備を導入すると、かえって総コストが高くなってしまう場合があります。たとえば、補助金を受けるために高性能な蓄電池を導入したものの、実際には電力消費量が少なく、費用対効果が十分でないケースも考えられます。そのため、補助金の条件に合わせるのではなく、自分たちのライフスタイルに合った住宅設計を優先することが重要です。
補助金を賢く活用して脱炭素住宅を実現しよう
脱炭素志向型住宅は、光熱費の削減や快適な住環境の実現といったメリットがある一方で、初期コストの高さやメンテナンスの負担といった課題もあります。しかし、国や自治体の補助金制度を活用することで、建築費用の負担を軽減し、長期的にコストを回収することが可能になります。
補助金を活用する際には、申請のタイミングや条件をよく確認し、無理のない資金計画を立てることが大切です。補助金だけに頼るのではなく、税制優遇措置も含めた総合的なコスト管理を行いながら、理想の脱炭素住宅を実現しましょう。
参照元:環境省「脱炭素志向型住宅の導入支援事業(子育てグリーン住宅支援事業)について」(https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/building_insulation/GX-house_00001.html)
参照元:環境省「脱炭素志向型住宅の導入支援事業(経済産業省・国土交通省連携事業)」【PDF】(https://www.env.go.jp/content/000293349.pdf)
参照元:国土交通省「子育てグリーン住宅支援事業について」(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000290.html)
PASSIVE STYLEが考える、本当に快適な高性能住宅の基準

PASSIVE STYLE

鹿児島で「高性能住宅」作りを専門に行う建築会社。ドイツのパッシブハウス研究所で習得したノウハウを日本に導入し、世界基準の断熱性能xパッシブスタイルによる、高性能住宅を数多く手がけている。設備ではなく、性能を活かして快適な生活をする。冬でも無暖房を可能とする住宅づくりに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
- 耐震等級3
国内最高値(※)の耐震性 - HEAT20 G3が標準仕様
全棟 UA値0.26/C値0.19の仕様で実現させる、高い断熱性と気密性 - 熱交換型の24時間換気システム
年間を通して快適な空気環境をキープ - こだわりの「パッシブデザイン」
夏は涼しく、冬は暖かい。自然エネルギーを活用する省エネな家
※参照元:【PDF】新築住宅の性能表示制度 かんたんガイド|国土交通省/令和4年11月7日版(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001586565.pdf)
鹿児島で「高性能住宅」作りを専門に行う建築会社。ドイツのパッシブハウス研究所で習得したノウハウを日本に導入し、世界基準の断熱性能xパッシブスタイルによる、高性能住宅を数多く手がけている。設備ではなく、性能を活かして快適な生活をする。冬でも無暖房を可能とする住宅づくりに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
- 耐震等級3
国内最高値(※)の耐震性 - HEAT20 G3が標準仕様
全棟 UA値0.26/C値0.19の仕様で実現させる、高い断熱性と気密性 - 熱交換型の24時間換気システム
年間を通して快適な空気環境をキープ - こだわりの「パッシブデザイン」
夏は涼しく、冬は暖かい。自然エネルギーを活用する省エネな家
※参照元:【PDF】新築住宅の性能表示制度 かんたんガイド|国土交通省/令和4年11月7日版(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001586565.pdf)


construction
PASSIVE STYLEで住宅を建てて
暮らし方が変わった方のお家をご紹介します。
インタビューもあるので、ぜひチェックしてみてください。