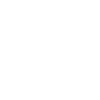このサイトは 「PASSIVE STYLE」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
一つの部屋だけを快適な室温にするエアコンとは異なり、建物全体の室温を均質に保つ全館空調。このページでは全館空調とは何か、導入するメリットを紹介します。
全館空調とは?
空気を循環させて、家全体を冷やす・暖める冷暖システムのこと。メーカーによって異なりますが、主に「天井吹き出し型」「床下冷暖房型」「輻射型」「壁掛けエアコン型」の4分類です。各部屋にエアコンを設置する必要がなく、一台で「換気・空気清浄・冷暖房」の三役をこなします。
全館空調のメリット
住宅性能を高める方法として「全館空調」という選択肢もあります。導入メリットを紹介するので、検討する際の判断材料にしてください。
家全体を均一温度に保てるため快適
全館空調を導入すると、家中どこにいても寒すぎる・暑すぎることなく快適に過ごせます。廊下・玄関・洗面所・トイレなど、エアコンでは対応できない場所まで冷やす・暖めることが可能。部屋ごとの温度差がないため、冬場にヒートショックのリスクを軽減できます。室温の変化を気にする必要がないため、ご高齢の方がいる家庭でも室内で起こる熱中症の心配をすることなく、安心して暮らせるでしょう。ペットのいる家庭にもおすすめです。
空気環境を清浄に保てるため衛生的
通常の住宅換気は、換気口から冷たい外気を取り入れます。寒い時期は換気口を閉じて換気が不十分になってしまうケースも。しかし天井から吹き出すタイプの全館空調の場合は、換気機能を備えているシステムがほとんどです。空気清浄システムが搭載されていればホコリ・花粉などの浮遊物を除去できます。花粉症に悩んでいる方にも嬉しいシステムと言えるでしょう。メーカーやシステムによって機能が異なるため、数社を見比べて検討するのがおすすめです。
メンテナンスの手間軽減に繋がる
全館空調は、各部屋に個別のエアコンを設置する必要がないため、メンテナンスが簡単になります。このシステムを採用することで、管理面でのストレスが大幅に軽減され、維持費の削減にもつながります。
- エアコン台数の削減:全館空調が一台で家全体を管理するため、エアコンの数を大幅に減らすことができます。これにより、複数のエアコンの掃除やメンテナンスに費やす手間と時間を大幅に短縮できます。
- フィルター交換のみで手間が少ない:全館空調のメンテナンスは、主にフィルター交換が中心で、手間がかかりません。さらに、フィルター交換の頻度が少ないシステムもあり、長期間にわたる運用が可能です。
- ダクト清掃による衛生管理:ダクト内の清掃が必要になる場合がありますが、専門業者による定期的なメンテナンスを行うことで、清潔な空気環境を保つことができます。
また、全館空調を導入することで、各部屋ごとの個別エアコンの故障リスクを削減できる点も大きなメリットのひとつ。一台のシステムで統合的に管理されるため、トラブル発生時の対応もスムーズです。
住宅のデザイン性の向上させやすい
全館空調を導入すると、各部屋にエアコンを設置する必要がなくなり、室内の見た目がすっきりします。デザイン性を重視する住宅では、インテリアとの調和を損なわない空調システムが求められます。
- インテリアの自由度:壁掛けエアコンが不要になるため、家具や装飾の配置に制約が少なくなります。これにより、デザイン性を重視したインテリアコーディネートが可能になります。
- 美観の向上:エアコンの配線や室外機の配置を気にする必要がなく、家全体のデザイン性が向上します。特にリビングやダイニングなど、人目に触れる空間では、この点が大きな魅力となります。
- 建築設計の自由度:全館空調を採用することで、建築デザインにおける空調設備の制約が減少し、より自由な設計が可能になります。
さらに、全館空調の導入により、省スペース化も実現できます。各部屋に設置されるエアコンの室外機が不要となるため、庭やベランダのスペースを有効活用できる点も魅力的です。
ランニングコストが削減できる
全館空調はエネルギー効率が高く、長期的にはコスト削減につながる可能性があります。特に、住宅の断熱性能が高い場合、その効果はさらに顕著になります。
- 高気密・高断熱との組み合わせ:高断熱・高気密の住宅と組み合わせることで、エネルギー消費を最小限に抑えられます。これにより、冷暖房にかかるランニングコストが大幅に削減されます。
- 無駄のない冷暖房:各部屋ごとにエアコンを使用するよりも効率的で、電気代が削減されます。さらに、全館空調は常に一定の温度を保つ設計が多いため、オン・オフの切り替えによるエネルギーロスが少ないのも特徴です。
- 省エネ型システムの採用:一部のメーカーでは、さらに効率的な運転が可能な省エネ型の全館空調システムを提供しており、環境負荷の軽減にも寄与します。
また、全館空調を使用することで、エアコンの同時稼働によるピーク電力の削減が可能です。これにより、住宅全体のエネルギー効率が向上し、持続可能な住環境を実現します。
全館空調のデメリットとは?
全館空調は、家全体の快適な温度を維持しやすい空調システムですが、その一方でデメリットも存在します。ここからは全館空調のデメリットを解説し、対策方法もあわせて紹介します。
導入コストが高くなってしまう
全館空調は一般的な個別エアコンの設置と比べて、初期導入コストが高額になってしまいます。その理由として、専用の空調設備やダクトが必要になること、施工費がかかること、さらに建築段階でシステムを組み込む必要があり住宅の設計に影響を与えるためです。また、導入に際しては設計の自由度が制限されるため、間取りや収納スペースに影響を及ぼす可能性があります。設置後に「思ったよりもスペースが狭くなった」と感じるケースもあるため、十分な検討が必要です。
対策方法
事前に複数の業者から見積もりを取得し、コストを比較することが重要です。また、省エネ住宅向けの補助金やローンを活用することで、初期費用の負担を軽減できます。全館空調の快適性や省エネ性能と初期コストを比較し、長期的な費用対効果を考慮することも検討すべきポイントです。
設計段階でしっかりと計画を立て、ダクトの配置や機器のサイズを最適化することで、余計な費用を削減できるでしょう。
ランニングコストが高くなる可能性
全館空調は家全体を24時間空調するため、電気代が高くなる傾向があります。特に気密性や断熱性の低い住宅では、外気の影響を受けやすく、余計なエネルギーを消費する可能性が高まってしまうでしょう。また、冷暖房の設定を適切に管理しなければ、電力の無駄遣いにつながることもあります。
対策方法
高断熱・高気密の住宅を選び、適切な断熱材や高性能な窓を使用することで、空調効率を向上させることが可能です。最新の省エネ技術を搭載した全館空調システムを導入することで、ランニングコストを抑えられます。また、エネルギーマネジメントシステム(HEMS)を活用し、電力使用状況を可視化することで効率的な運用が可能です。
さらに、部屋ごとの温度を細かく管理できるシステムを導入し、必要なエリアだけ冷暖房を稼働させることで、電力消費を最適化できます。
メンテナンスが必要で手間がかかる
全館空調は空気を循環させるため、フィルターやダクト内にホコリやカビが溜まりやすくなります。そのため、定期的な清掃やメンテナンスが必要です。特にダクト内の清掃は専門業者に依頼することが多く、メンテナンス費用がかかる点も考慮しましょう。
対策方法
専門業者との定期点検契約を結ぶことで、清掃や点検を計画的に行えます。また、フィルターの清掃や交換は自分で行うことで、コストを抑えることが可能です。また、メンテナンスが簡単なフィルターを選んだり、使用期限の長いフィルターを使用したりするとよいでしょう。
故障時に家全体の空調が停止するリスクがある
全館空調が故障すると、家全体の空調が停止し、修理が完了するまでの間、快適な環境を維持することが難しくなります。特に夏場や冬場では、室内の温度変化が健康に影響を及ぼす可能性もあります。修理には時間とコストがかかり、部品の取り寄せや業者の対応状況によっては数週間かかる場合もあります。
また、全館空調は一般的なエアコンとは異なり、複雑な配管や制御システムを使用しているため、故障の原因を特定するのに時間がかかることもあるでしょう。
対策方法
故障を未然に防ぐために、定期点検を実施し、異常の兆候を早期に発見することが大切。メーカーが推奨しているメンテナンススケジュールを守り、フィルターやダクトの清掃を定期的に行うことで、故障リスクを軽減できます。また、ポータブルエアコンやヒーターを用意しておくと、万が一の際にも対応しやすくなります。
保証期間の延長や修理費用をカバーする保険に加入することで、長期的なメンテナンス費用の負担を軽減することに繋がるでしょう。
部屋ごとの温度調整が難しい
全館空調は家全体の温度を一定に保つため、部屋ごとに細かい温度調整が難しくなってしまいます。家族それぞれの体感温度が異なる場合、一部の人には快適でも、他の人には寒すぎる、または暑すぎると感じることがあるもの。特に日当たりや風通しの影響で、部屋ごとの温度差が生じやすくなるでしょう。
また、使用頻度の異なる部屋にも均等に冷暖房が行き渡るため、実際にはあまり使用しない部屋の空調にも電力が消費されてしまう可能性があります。これにより、無駄なエネルギー消費が発生し、ランニングコストが増加することもゼロではありません。
対策方法
住宅全体の温度を維持しながらも、部屋ごとの空調整備ができるゾーニングシステムを導入することで、エリアごとに温度調整が行えます。また、補助的な暖房や冷房機器を活用することで、より柔軟な温度管理ができるでしょう。
空気が乾燥しやすい
全館空調は空気を循環させるため、特に冬場の暖房時に湿度が低下しやすくなります。これにより、肌の乾燥や喉の不快感を引き起こし、風邪やインフルエンザのリスクが高まる可能性があります。また、過度な乾燥環境では、ホコリやアレルギー物質が空気中に舞いやすくなり、アレルギー症状を悪化させる原因になることも。特に、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、適切な湿度管理が健康維持のために大切になるでしょう。
対策方法
加湿器を使用したり、加湿機能付きのエアコンを利用したりすることで適切な湿度を維持できます。また、観葉植物を室内に配置すると、自然な湿度調整が可能になったり、調湿機能のある建材を使用したりすることで、湿度の変動を抑え、快適な空間を維持しやすくなるでしょう。
最近では、全館空調に加湿機能を組み込んだシステムも開発されており、これを導入することで乾燥対策をより効果的に行えます。

PASSIVE STYLE

鹿児島で「高性能住宅」作りを専門に行う建築会社。ドイツのパッシブハウス研究所で習得したノウハウを日本に導入し、世界基準の断熱性能xパッシブスタイルによる、高性能住宅を数多く手がけている。設備ではなく、性能を活かして快適な生活をする。冬でも無暖房を可能とする住宅づくりに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
- 耐震等級3
国内最高値(※)の耐震性 - HEAT20 G3が標準仕様
全棟 UA値0.26/C値0.19の仕様で実現させる、高い断熱性と気密性 - 熱交換型の24時間換気システム
年間を通して快適な空気環境をキープ - こだわりの「パッシブデザイン」
夏は涼しく、冬は暖かい。自然エネルギーを活用する省エネな家
※参照元:【PDF】新築住宅の性能表示制度 かんたんガイド|国土交通省/令和4年11月7日版(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001586565.pdf)
鹿児島で「高性能住宅」作りを専門に行う建築会社。ドイツのパッシブハウス研究所で習得したノウハウを日本に導入し、世界基準の断熱性能xパッシブスタイルによる、高性能住宅を数多く手がけている。設備ではなく、性能を活かして快適な生活をする。冬でも無暖房を可能とする住宅づくりに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
- 耐震等級3
国内最高値(※)の耐震性 - HEAT20 G3が標準仕様
全棟 UA値0.26/C値0.19の仕様で実現させる、高い断熱性と気密性 - 熱交換型の24時間換気システム
年間を通して快適な空気環境をキープ - こだわりの「パッシブデザイン」
夏は涼しく、冬は暖かい。自然エネルギーを活用する省エネな家
※参照元:【PDF】新築住宅の性能表示制度 かんたんガイド|国土交通省/令和4年11月7日版(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001586565.pdf)


construction
PASSIVE STYLEで住宅を建てて
暮らし方が変わった方のお家をご紹介します。
インタビューもあるので、ぜひチェックしてみてください。