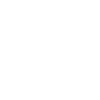このサイトは 「PASSIVE STYLE」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
これから長く住む家ですから、夏は涼しく冬は暖かい家が良いと思うのは当然ですよね。ここでは、家の断熱材に迷っている方に向けて、断熱材の種類とそれぞれの特徴を詳しく解説しています。
そもそも断熱材が担っている役割とは?
断熱材の最大の役割は、家の内外の温度差を抑えて快適な室内環境を保つことです。夏は外からの熱を遮り、冬は室内の暖気を逃がさないようにすることで、冷暖房の効率を高め、光熱費の節約にもつながります。
また、断熱性能が高いと結露が発生しにくく、カビや腐朽の原因を減らせるため、建物の耐久性や住まいの健康性を向上させる効果も期待できます。
断熱材には「熱を伝えにくい性質」をもつ素材が使われており、ロックウールやグラスウール、発泡プラスチック系、セルロースファイバーなど多彩な種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあるため、住まいの構造や予算、気候条件に合わせて選ぶことが大切です。
無機繊維系の断熱材
グラスウール
グラスウールは、溶解したガラスや鉱物を遠心力で繊維状に引き延ばして成形した断熱材です。その内部に無数の空気層を形成することで熱を伝えにくくし、住宅の壁・天井・床などに広く用いられています。また、多くはリサイクルガラスを原料としており、環境配慮型の素材でもあります。
メリット
- コストパフォーマンスに優れる:原料がガラス破片などの再生材を含むため、他の断熱材に比べて価格が安く抑えられる
- 耐久性が高い:無機物であるため化学変化を起こしにくく、長期間使用しても性能劣化が少ない
- 難燃性・高温耐性が高い:ガラス素材ゆえに燃えにくく、万一の火災時にも有毒ガスをほとんど発生しない。
- 加工性が良い:綿状であるためカットや曲げがしやすく、複雑な形状のスペースにも隙間なく施工しやすい
デメリット
- 湿気に弱い:繊維自体に吸水性はないものの、繊維間に空気として保持された水分が断熱性能を著しく低下させるため、防湿シートの併用が必要
- 施工時に気密確保が難しい:隙間が生じるとせっかくの断熱性能が発揮されにくくなるため、知識・経験ある施工業者による丁寧な施工が求められる
ロックウール
ロックウールは、玄武岩や製鋼スラグなどの鉱物を溶融し、繊維状にした断熱材です。密度が高く、グラスウール同様に繊維間の無数の空気層が断熱効果を生み出します。
メリット
- 耐火性・耐熱性が非常に高い:鉱物由来なので火災時にも形状がほとんど崩れず、有害ガスの発生も少ないため、防火対策を重視する住宅に向いている
- 撥水性に優れる:グラスウールより湿気への耐性がやや高く、ある程度の水分をはじくため、湿度の高い場所でも使いやすくなっている
デメリット
- 価格が高い:グラスウールと比べて原料コストおよび製造コストが上乗せされ、施工単価がやや高くなる
- 吸湿による断熱性能低下のリスク:湿気を吸収すると断熱性能が著しく低下するため、防湿処理や施工時の配慮が必要
木質繊維系
セルロースファイバー
セルロースファイバーは、新聞古紙や段ボールなどをリサイクルしてパルプ状に加工した断熱材で、綿状の繊維を吹き込むように施工します。ホウ酸・硫酸アンモニウム等で防虫・防火処理が施されています。
メリット
- 優れた調湿機能:木質セルロースの微細な繊維構造により、室内の余分な湿気を吸放湿し、結露やカビ発生を抑える
- 防音・吸音性が高い:繊維の絡み合い構造が音を拡散・吸収するため、遮音性能が向上する
- 人体に優しい:化学接着剤をほとんど使わず、火災時にも有害ガスの発生が少ないとされ、アレルギー等への影響も少ないと言われている
デメリット
- 価格が高め:無機繊維系よりも製造コストや施工コストが割高になりやすく、材料費だけで比較するとコスト負担が大きい
- 沈下・偏りのリスク:吹き込み施工後に重力で繊維が沈下し、断熱材に隙間が生まれると断熱性能が低下する可能性がある。そのため専用の吹き込み工法や撥水処理が必要になる。
天然素材系
ウールブレス(羊毛)
羊毛(ウール)を繊維状のまま断熱材化し、ホウ酸などで防虫処理を施した素材です。自然素材ならではの柔らかさで、細かな隙間にも馴染みやすく施工性に優れます。
メリット
- 高い調湿性:ウール自体が湿気を吸放出する機能を持つため、過度な室内湿度を緩和し、結露を抑制する
- 優れた断熱性:繊維間に含まれる空気層が熱を遮断し、同等厚みのほか素材と比較しても高い断熱効果を発揮する場合がある
- 防音・吸音性:羊毛の繊維構造が音を拡散・吸収し、防音性能が向上する
- 耐久性:適切に処理されたウールは繊維が崩れにくく、長期間にわたり断熱性能を維持しやすいと言われている
デメリット
- 施工業者が少ない・コスト高:取り扱い業者数が限られており、材料・施工費用ともに高めになる傾向がある
- 湿気やダニへの配慮:ウールは素材自体が湿気を吸いやすく、高湿環境下ではダニやカビの発生リスクがあるため、防虫・防カビ処理を徹底する必要がある
炭化コルク
コルク樫から採取したコルク材を高温・無酸素下で炭化させた断熱材です。内部に多孔質の空気層を持ち、断熱・調湿・吸音性など幅広い性能を発揮します。
メリット
- 高い断熱性能:多孔質構造により熱伝導を抑制し、厚みを抑えても優れた断熱性を発揮する
- 優れた調湿性・吸音性:コルクの天然繊維構造が湿気を緩やかに吸放湿し、かつ音を吸収するため、室内環境を快適に保ちやすい。
- 防虫・防カビ性:コルク自体に天然の防虫成分が含まれており、ダニやカビの発生リスクを低減できる
デメリット
- 非常に高価:原材料のコルク樫や炭化加工のコストが高い傾向にある
- 施工性の制約:硬質であるため、既存住宅のリフォーム時など狭い隙間への施工が難しく、専用接着剤や工法が必要になる
発泡プラスチック系
ポリスチレンフォーム
ポリスチレン樹脂をビーズ状にして発泡剤を加えた断熱材で、発泡ビーズ同士を加熱融着して板状に成形したものを「ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)」と呼びます。軽量で撥水性に優れ、外張り断熱や床下断熱などに広く用いられます。
メリット
- 高い撥水性:セルを気泡構造で閉じ込めているため、水をほとんど吸わず、湿気の多い部位でも断熱性能が維持されやすい
- 軽量・施工しやすい:板状になっているためカットや運搬が容易で、外壁・基礎まわりなどへの施工が比較的簡単
デメリット
- 耐熱性が低い:高温環境下では変形・収縮を起こしやすく、特に外付けの場合は遮熱対策(遮光・遮熱塗装など)が必要になることがある
- 燃焼時の有毒ガス発生:ポリスチレン系は燃え始めると炎が急速に広がりやすく、有毒な煙を発生するため、防火対策が不可欠。
- 環境負荷:製造工程で発泡剤にフロン系ガスが使われる場合があり、地球温暖化係数(GWP)の高い素材も存在する
硬質ウレタンフォーム
ポリウレタン樹脂に発泡剤を加えて現場吹付、または工場でボード化した断熱材です。現場吹付タイプは施工後に発泡拡張して隙間を埋め、気密性を高められます。
メリット
- 高い断熱性能:熱伝導率が極めて低く、薄い厚みでも十分な断熱効果を実現する
- 気密性が向上:現場吹付けの場合、複雑な形状の壁や梁周りにも発泡材が隙間なく充填されるため、気密性を確保しやすい
- 施工がスピーディー:吹付後すぐに硬化するため、施工時間が短く工期を短縮できる
デメリット
- シロアリ被害のリスク:セルロース系と同様にシロアリの好む栄養源とはなりませんが、木部との接触部や隙間があるとシロアリ被害を受けやすいという報告もある。施工時に防蟻対策が必要になる
- 燃焼時の有毒ガス発生:耐火ボード等で保護しないと火災時にシアンガスなどの有毒ガスが発生するため、防火被覆の適用が必須
- 経年収縮・隙間の発生:長期間経過すると微量ながら収縮し、わずかな隙間が生じることがあり、定期的な点検が望まれる
フェノールフォーム
フェノール樹脂に発泡剤・硬化剤を混ぜて成形した断熱材で、セル構造が細かく均質なため、熱伝導率が非常に低い点が特徴です。
メリット
- 高い断熱性能:同厚みで比べた場合、ポリウレタンやEPSよりもさらに低い熱伝導率を実現し、薄型で高い断熱性能を発揮する
- 優れた耐火・耐水性:フェノール樹脂自体が燃えにくく、結露水による劣化も生じにくい構造のため、耐久性が非常に高い
- 寸法安定性:発泡セルが細かく均一なので、温度変化や湿度変化による収縮・膨張が少なく、長期にわたって安定した断熱性能を維持できる
デメリット
- 価格が非常に高い:原料コストが高く、施工単価も上昇するため、一般的には高級仕様の住宅や防火地域などに限定されることが多い
- 施工性に配慮が必要:硬質ボードのため、現場での切断や加工に手間がかかり、また接合部の気密処理を丁寧に行わないと断熱欠損を起こしやすい
断熱材を選ぶ前に知りたい施工方法
断熱材をどのように敷き詰めるかによって、性能やコスト、施工難易度が変わります。ここでは代表的な3つの工法を紹介します。
充填断熱(内断熱)工法
壁や天井、床の内側に断熱材を充填する方法です。既存の柱と柱の間に綿状やボード状の断熱材を隙間なく詰め込むことで、比較的ローコストに施工できます。
メリット
- 施工費用が抑えられる
- あらゆる断熱材が利用可能
- 工事範囲が室内側だけなのでリフォーム時に手軽
デメリット
- 柱や梁の周りに隙間が生じやすく、気密性確保が難しい
- 防湿シートの施工が不十分だと結露リスク増大
- 工事中に室内の片付けや養生が必要
外張り断熱(外断熱)工法
建物の構造躯体の外側に断熱材を張り付け、さらに下地や外装を重ねる工法です。家全体をすっぽり包むイメージで、隙間なく連続的に断熱層を形成できます。
メリット
- 柱や梁の影響を受けず、均一な断熱性能を発揮
- 気密性・断熱性能が高く、省エネ効果が大きい
- 躯体の結露リスクを抑え、構造の長寿命化に貢献
デメリット
- 施工費用や工期が長くなりがち
- 外観デザインやサッシの取り合いに配慮が必要
- 地震などの揺れで断熱材が落下するリスク対策が必要
付加断熱工法
充填断熱と外張り断熱を組み合わせ、さらに断熱層を増設する工法です。内側と外側の両面から断熱を強化するため、非常に高い断熱性能を実現できます。
メリット
- 断熱厚みを増せるため、住宅の断熱性能を極限まで高められる
- 外断熱で熱橋(断熱の弱点)をカバーしつつ、内断熱で隙間を補える
- 快適性が最も向上し、ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)にも対応
デメリット
- 材料・施工費用が大幅にアップ
- 壁厚が厚くなり、室内面積が狭くなる可能性
- 設計段階での調整が複雑
断熱材選びのポイント
家づくりやリフォームを考えるとき、断熱材をどう選ぶかはとても大切です。断熱材の性能によって冬の寒さや夏の暑さが大きく左右されるだけでなく、冷暖房にかかる光熱費や結露・カビなどのリスクにも影響するからです。ここでは、断熱材選びで押さえておきたいポイントを4つご紹介します。
建物の構造や立地、気候に合ったタイプを選ぶ
まずは、お住まいの構造や地域の気候に合った断熱材を選ぶことが大切です。たとえば寒さが厳しい地域では、熱伝導率が低く厚みを確保しやすいものを選ぶと、室内の暖かさを逃がしにくくなります。一方、夏場の湿度や日差しが気になる地域では、遮熱性や防湿性に優れたタイプを検討すると快適性が向上します。
木造・鉄骨造・RC造など建物によって適した工法も異なるため、専門家に相談しながら構造に合った断熱材を使うことがポイントです。
長期的なメリット・デメリットや維持費も考慮する
断熱材は、初期費用だけでなく長期的なメリットも踏まえて検討しましょう。高性能な素材は導入コストが高い反面、冷暖房費が抑えられるため、トータルでお得になる可能性があります。
逆に手ごろな価格の断熱材でも、きちんと施工すれば十分な効果を発揮することがあります。経年劣化の度合いや、交換・補修が必要になるタイミングなども含めて考えると、最適な選択がしやすくなります。
防火性・防蟻性・耐久性などへの配慮も必要
特に木造住宅であれば、シロアリ被害や火災時の安全性は重要なチェックポイントです。発泡系の断熱材は燃えやすいイメージがある一方で、難燃剤入りのタイプや、そもそも燃えにくい素材もあります。シロアリ対策が施されている断熱材もあり、これらをうまく組み合わせることでリスクを軽減できます。湿気による結露やカビの発生を防ぐためにも、素材の耐久性や調湿性能を調べると安心です。
長期的な観点で建物を守るためにも、耐久性が高いかどうかをしっかりチェックしましょう。
信頼できる施工会社に相談して、適切な工法を確認する
どんなに優秀な断熱材を用意しても、施工が不十分だと性能を発揮しきれません。充填断熱や外張り断熱、付加断熱など工法ごとに特徴があり、建物の構造や予算、仕上がりのイメージによって選択が変わります。経験豊富な施工会社なら、住宅全体のバランスや将来のメンテナンスも含めてアドバイスしてくれるでしょう。実績や口コミなどを調べ、丁寧な説明やサポートが期待できる業者を見つけることが、失敗しない断熱材選びへの近道です。
まとめ
断熱材にはさまざまな種類があり、それぞれメリットやデメリットが存在します。価格にも差があるため、希望の断熱材を使いたい場合は施工業者と相談の上、予算に見合ったものを検討すると良いでしょう。

PASSIVE STYLE

鹿児島で「高性能住宅」作りを専門に行う建築会社。ドイツのパッシブハウス研究所で習得したノウハウを日本に導入し、世界基準の断熱性能xパッシブスタイルによる、高性能住宅を数多く手がけている。設備ではなく、性能を活かして快適な生活をする。冬でも無暖房を可能とする住宅づくりに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
- 耐震等級3
国内最高値(※)の耐震性 - HEAT20 G3が標準仕様
全棟 UA値0.26/C値0.19の仕様で実現させる、高い断熱性と気密性 - 熱交換型の24時間換気システム
年間を通して快適な空気環境をキープ - こだわりの「パッシブデザイン」
夏は涼しく、冬は暖かい。自然エネルギーを活用する省エネな家
※参照元:【PDF】新築住宅の性能表示制度 かんたんガイド|国土交通省/令和4年11月7日版(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001586565.pdf)
鹿児島で「高性能住宅」作りを専門に行う建築会社。ドイツのパッシブハウス研究所で習得したノウハウを日本に導入し、世界基準の断熱性能xパッシブスタイルによる、高性能住宅を数多く手がけている。設備ではなく、性能を活かして快適な生活をする。冬でも無暖房を可能とする住宅づくりに興味がある方は、ぜひチェックしてみてください。
- 耐震等級3
国内最高値(※)の耐震性 - HEAT20 G3が標準仕様
全棟 UA値0.26/C値0.19の仕様で実現させる、高い断熱性と気密性 - 熱交換型の24時間換気システム
年間を通して快適な空気環境をキープ - こだわりの「パッシブデザイン」
夏は涼しく、冬は暖かい。自然エネルギーを活用する省エネな家
※参照元:【PDF】新築住宅の性能表示制度 かんたんガイド|国土交通省/令和4年11月7日版(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001586565.pdf)


construction
PASSIVE STYLEで住宅を建てて
暮らし方が変わった方のお家をご紹介します。
インタビューもあるので、ぜひチェックしてみてください。